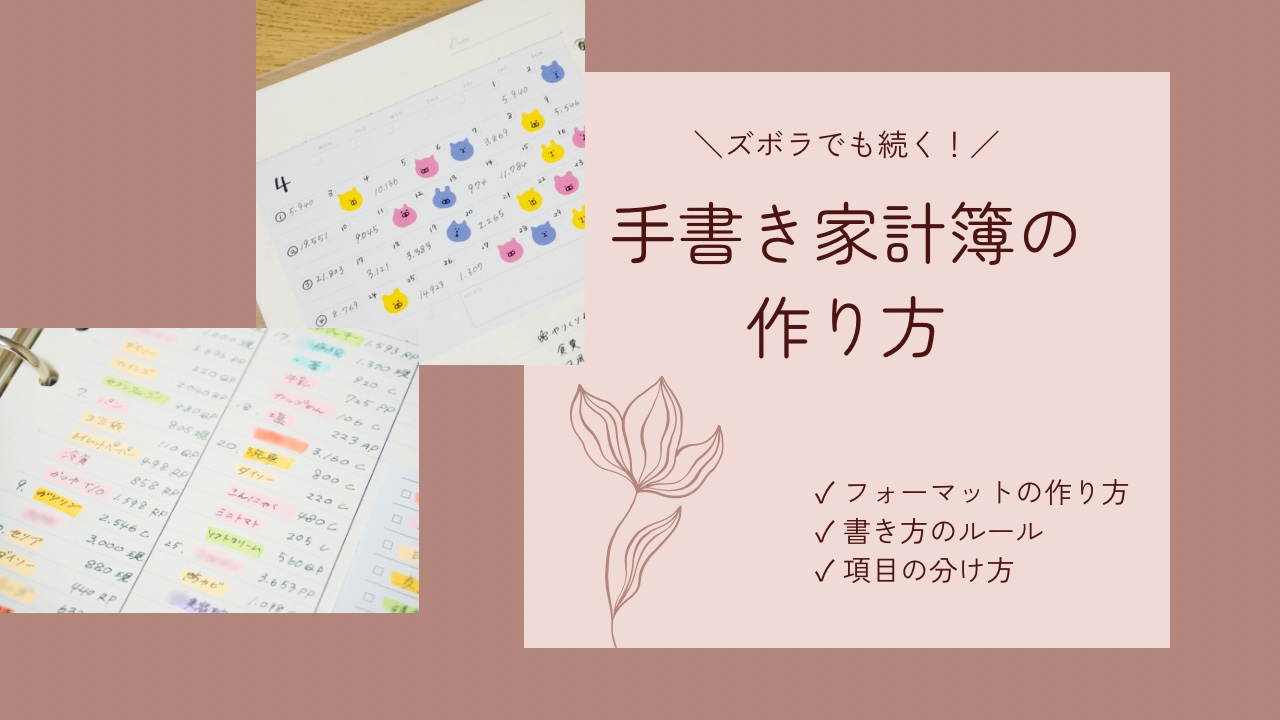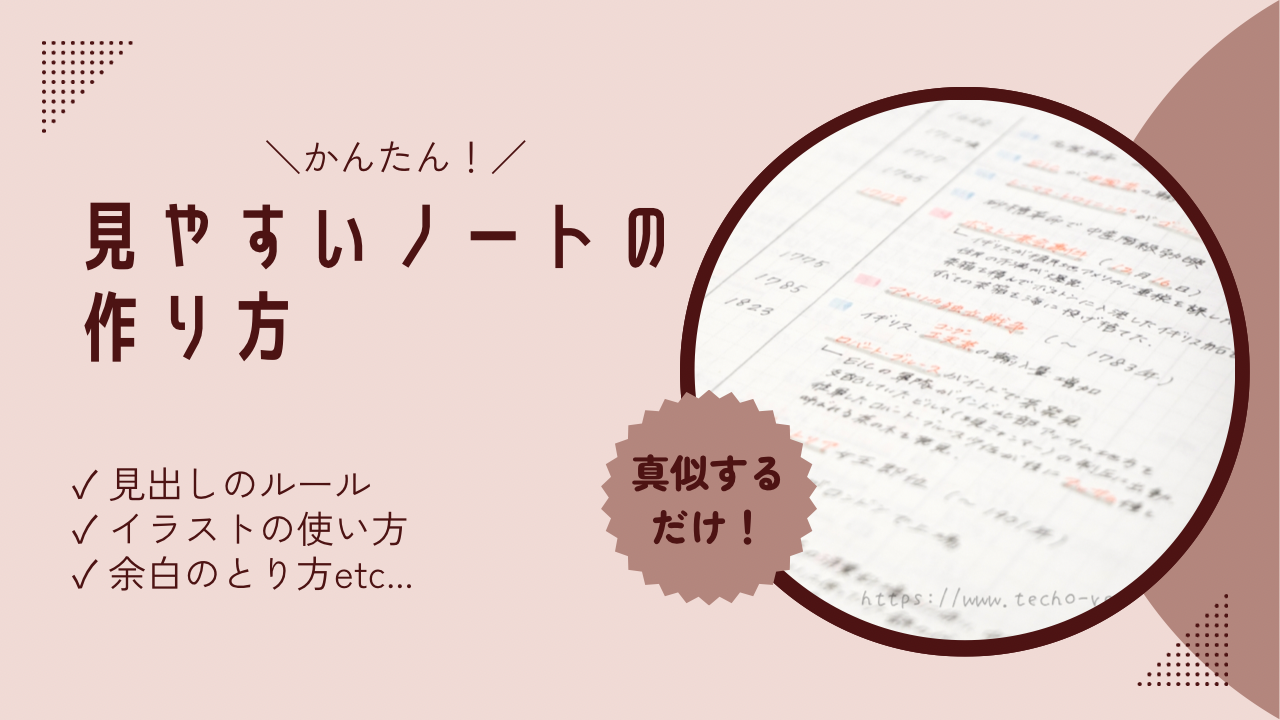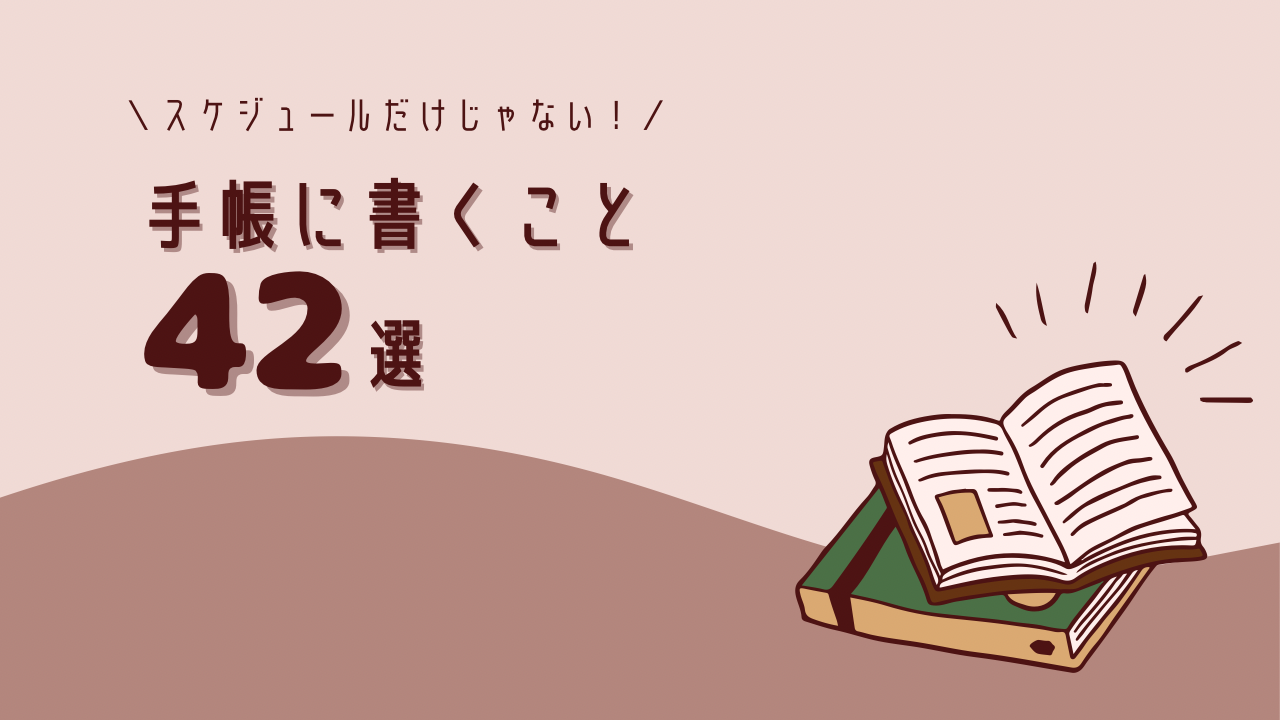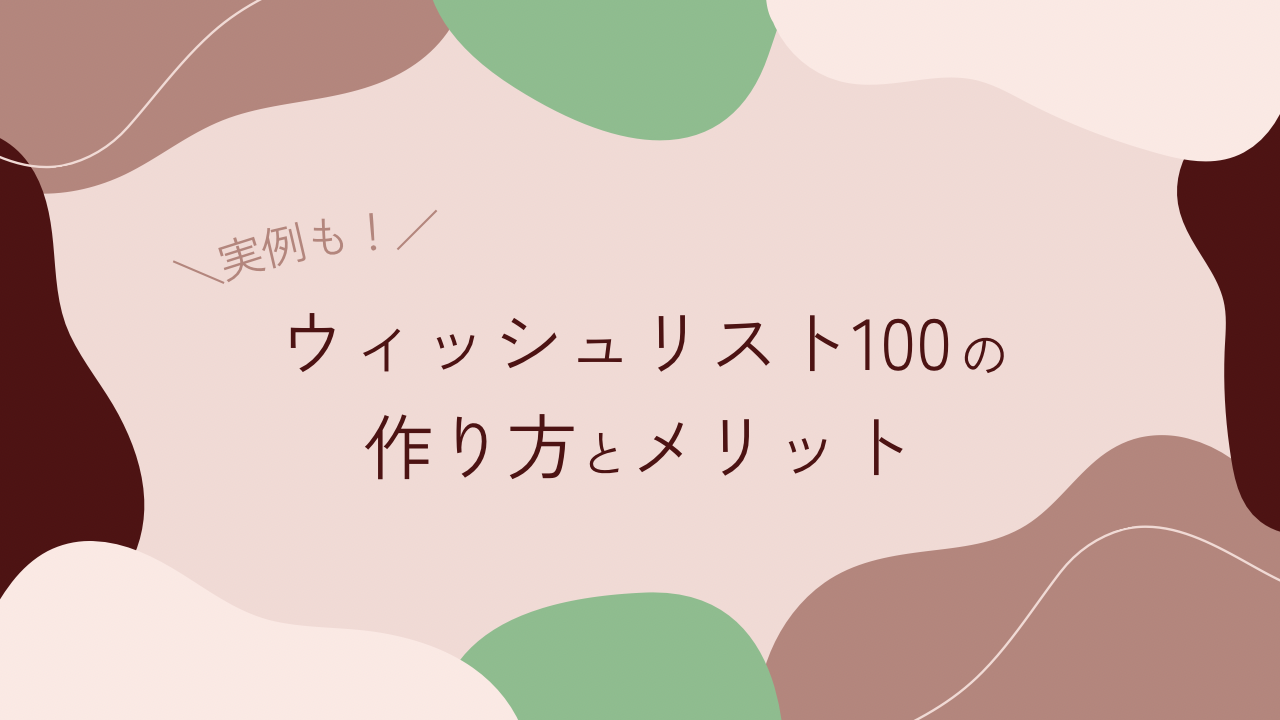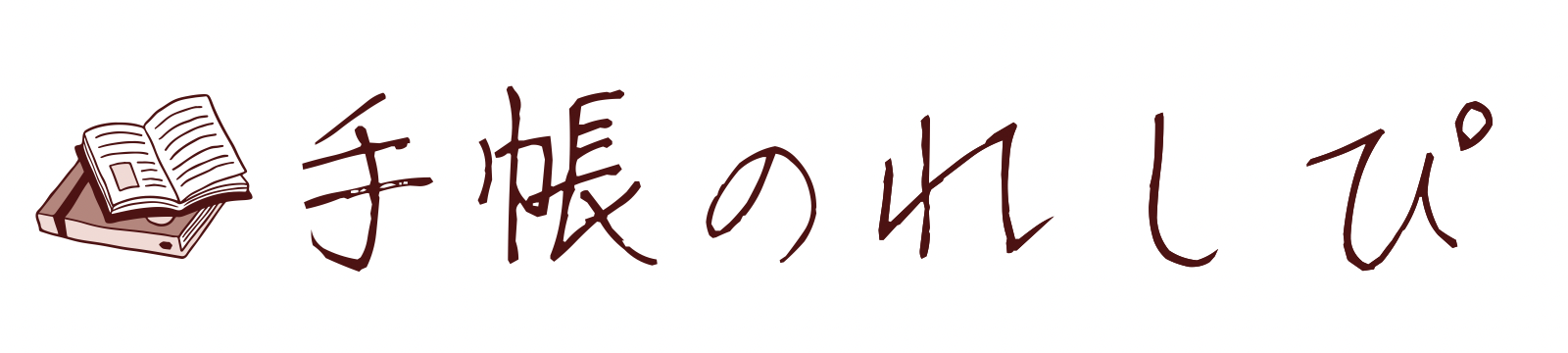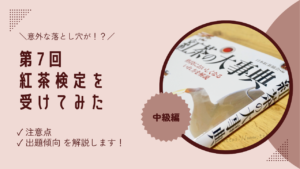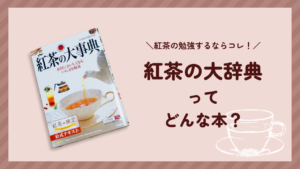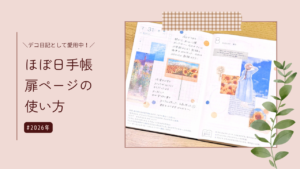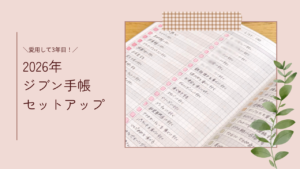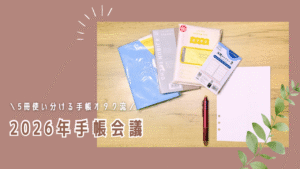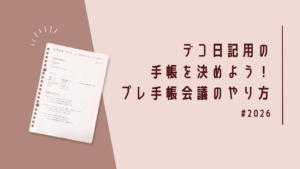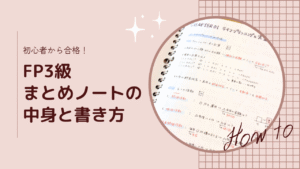紅茶検定を受けるなら何級?級位の選び方と難易度を解説!

紅茶検定は紅茶のいれ方や産地など、「紅茶」にまつわる幅広い知識を問う民間資格です。
勉強はテキスト一冊のみ、独学で合格が目指せるので、まとまった勉強時間がとれない社会人の方でも気軽に受験できます。
しかし、紅茶検定は比較的新しい資格ということもあり、公式問題集や過去問題集が販売されていません。
そのため、「興味はあるけど勇気が出なくて受けられない」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
そこで本記事では、私が実際に勉強してみて感じた難易度と受験級の決め方をご紹介していきます。
「紅茶検定に興味がある」
「紅茶の勉強をしてみたい」
という方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
【2025年7月追記】
プロフェッショナル(上級)廃止・料金改定にともない、一部内容を修正しました。
紅茶検定について
紅茶検定は紅茶検定実行委員会が主催する民間資格です。
日本唯一の紅茶団体である日本紅茶協会の協力のもと開催されています。
出典:紅茶検定 公式サイト
| 主催 | 紅茶検定実行委員会 特別協力:日本紅茶協会 |
| 級位 | ベーシック(初級) アドバンス(中上級) |
| 検定料 | ベーシック:5,000円 アドバンス:6,500円 |
| 勉強方法 | 公式テキスト |
| 受験方法 | オンライン(PC/スマホ/タブレット) |
| 試験時間 | 60分 |
| 問題数 | 80問 |
| 出題形式 | マークシート式(四者択一) |
| 合格ライン | 概ね正解率70%以上 |
| 試験日程 | 年2回程度 |
※2025年7月現在の情報です。最新情報は公式サイトをご確認くださいませ。
試験はオンラインで行います。
スマートフォンやカメラ付きのPC、タブレットとインターネット環境があれば全国どこにいても受験が可能です。
紅茶検定を受けるなら何級?
紅茶検定は公式テキストから出題されるため、誰でも気軽に受験できます。
いきなりアドバンスを受けるといった「飛び級」も可能です。

ここからは紅茶検定の各級ごとの難易度、特徴、そして受験級の決め方をご紹介していきます。
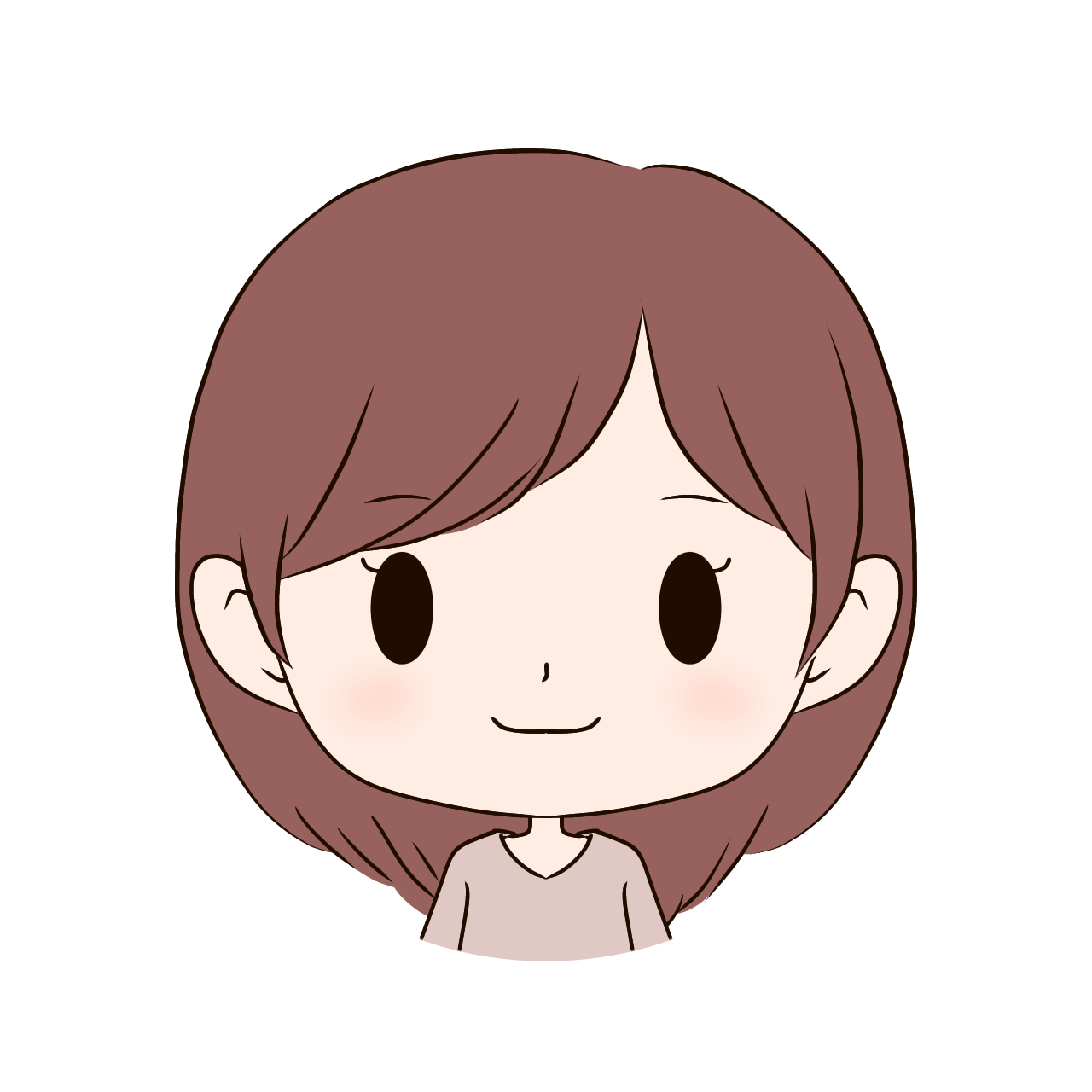
ちなみに、私は「趣味として検定の勉強をしつつ紅茶の知識も深めたい」と思っていたので、最初から中級を受験しました。
ベーシック:まずはここから!
ベーシックは最も難易度が低い級です。
紅茶のいれ方や製造方法、保存方法、産地と茶葉の知識、各国の歴史や文化など紅茶の基礎について出題されます。
| 合格ライン | 概ね正解率70%以上 |
| 合格率 | 約85% |
| テキスト | 『紅茶の大辞典 |
| 勉強期間(目安) | 1ヶ月 |
テキストはアドバンスと共通ですが、初級は主要なポイントを中心に出題されます。
重要な箇所をしっかり押さえておけば十分に合格を目指せるので、勉強時間があまり取れない方でも気軽に受験しやすいでしょう。
例題を見てみましょう。
【例題】
出典:紅茶検定 練習問題(初級)
- 紅茶を急に冷やすと白く濁ってしまう現象を何というか。
- 「チャ」の木は学名で何というか。
ベーシックは「○○を何というか」というように、語句を選ぶ問題が多くなっています。
テキストに登場する語句は見逃さずにチェックしておきましょう。
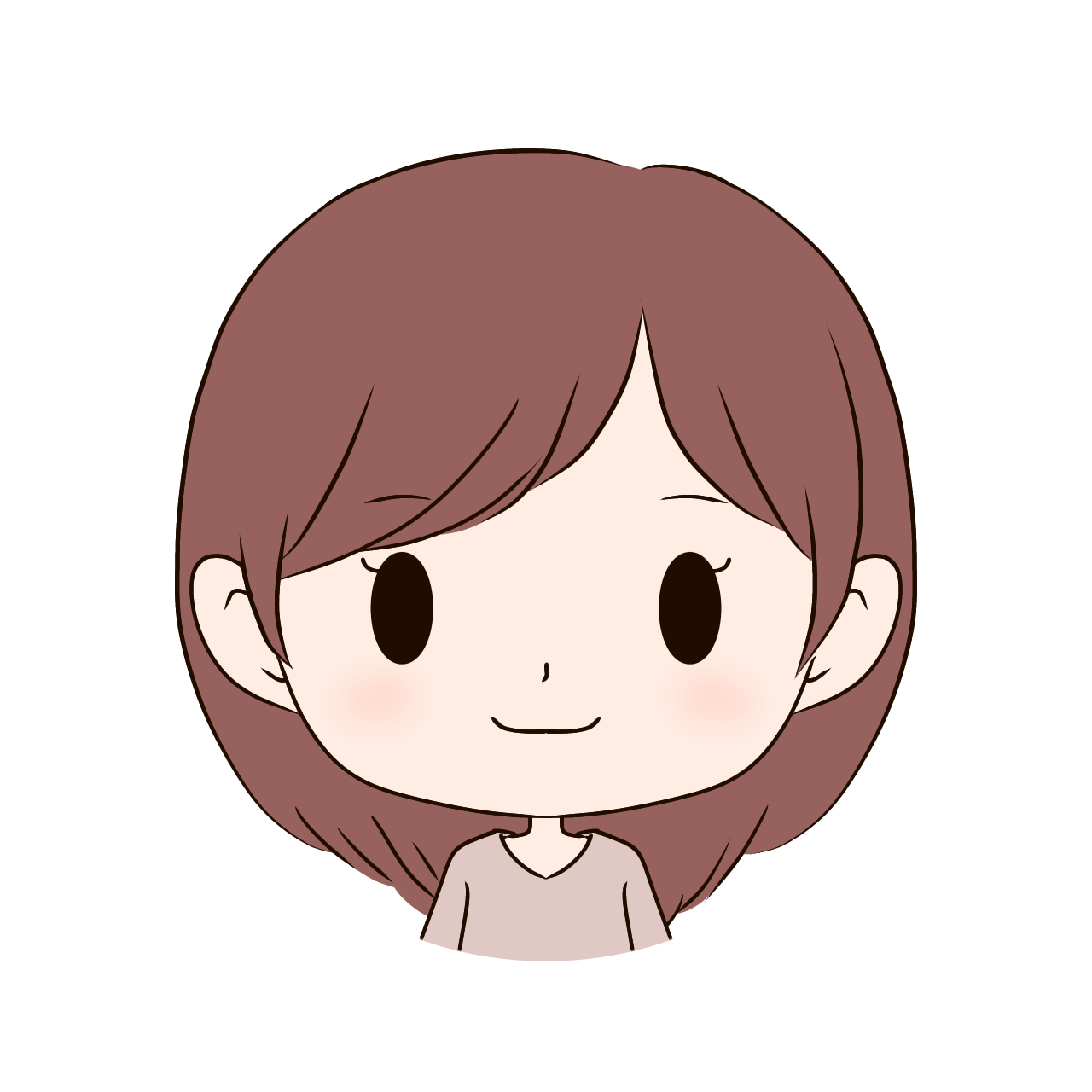
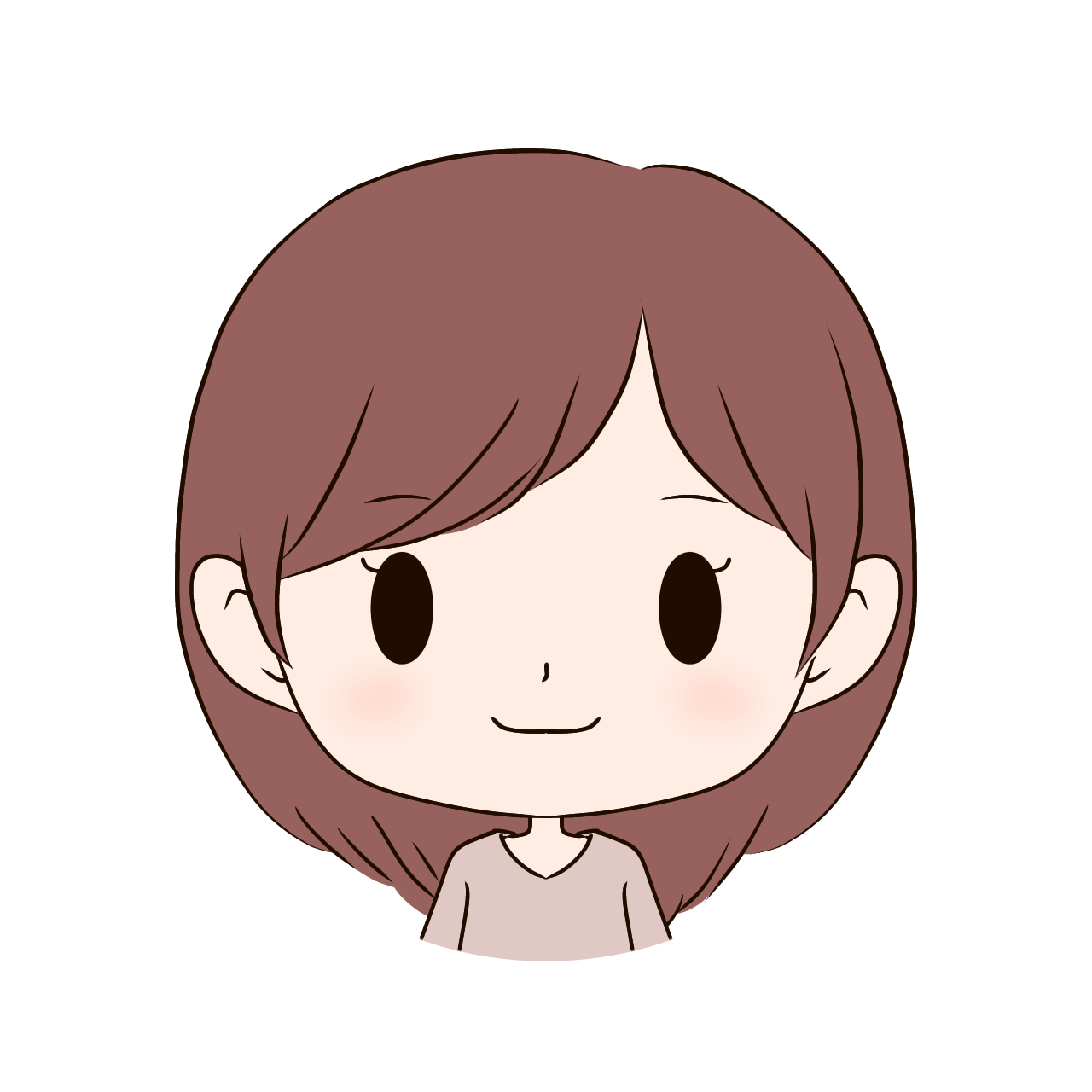
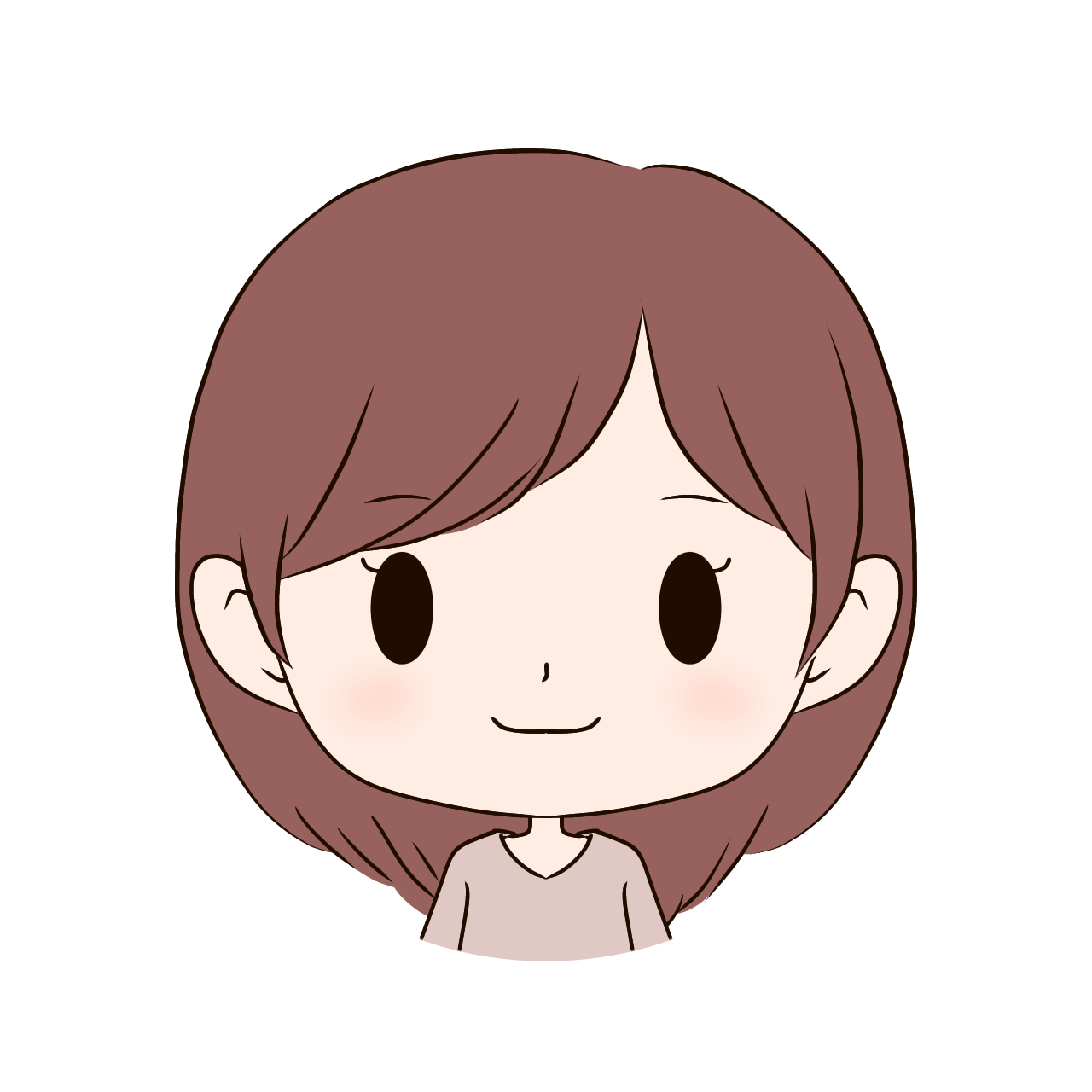
覚えたい語句と説明文にマーカーを引いて何度も読み返すのがおすすめ!
ベーシックは合格率が約85%と高く、初心者でも気軽に受験できます。
「紅茶の勉強をしてみたい」「気軽に受けたい」という方は、まずはベーシックにチャレンジするのがおすすめです。
- 紅茶について初めて学ぶ
- 手軽に検定を受けたい
- 勉強時間があまりとれない
紅茶検定は合格するとカレルチャペック紅茶店特製イラスト入りの合格認定書がもらえます。
級位によってデザインが異なるので、全級合格を目指してみるのもいいですね。
アドバンス:幅広い知識を身につけたい!
アドバンスはベーシックの範囲に加え、マーケット、品質や規格、成分と効能などさらに深い紅茶の知識が問われます。
| 合格ライン | 概ね正解率70%以上 |
| 合格率 | 約75% |
| テキスト | 『紅茶の大辞典 |
| 勉強期間(目安) | 2ヶ月 |
ベーシックに比べて難易度は上がるものの、短期間でも十分に合格を狙えます。
メインテキストは、同じく『紅茶の大辞典
アドバンスは出題範囲が増えるため、テキストをくまなく勉強しましょう。
さらに、公式サイトから購入できる『紅茶検定 アドバンス用テキスト』が補助テキストに認定されています。
例題を見てみましょう。
【例題】
出典:紅茶検定 練習問題(中級)
- 日本の紅茶の輸入先で最も量が多い国はどこか。
- キャッスルトン、マーガレッツホープ、ジュンパナ等の茶園でとれるお茶は何か。
このほか、アドバンスでは「○○でないものはどれか」というような、選択肢の中から間違っているものを探す問題もあります。
しっかり内容を理解していないと答えられないものも多いので、テキストをしっかり読み込んでおく必要があります。
重要語句は名称だけでなく、説明ができるようにしておくといいでしょう。
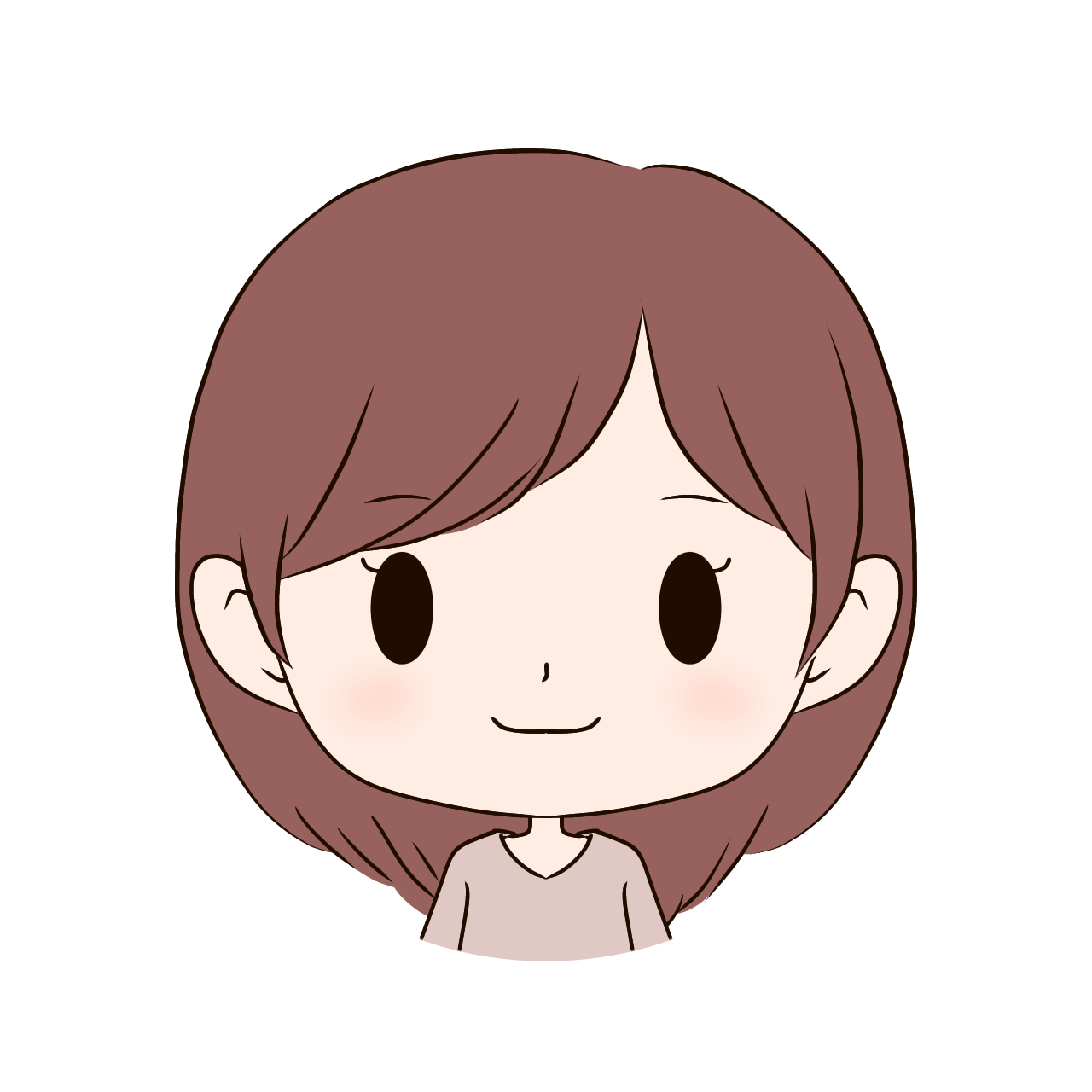
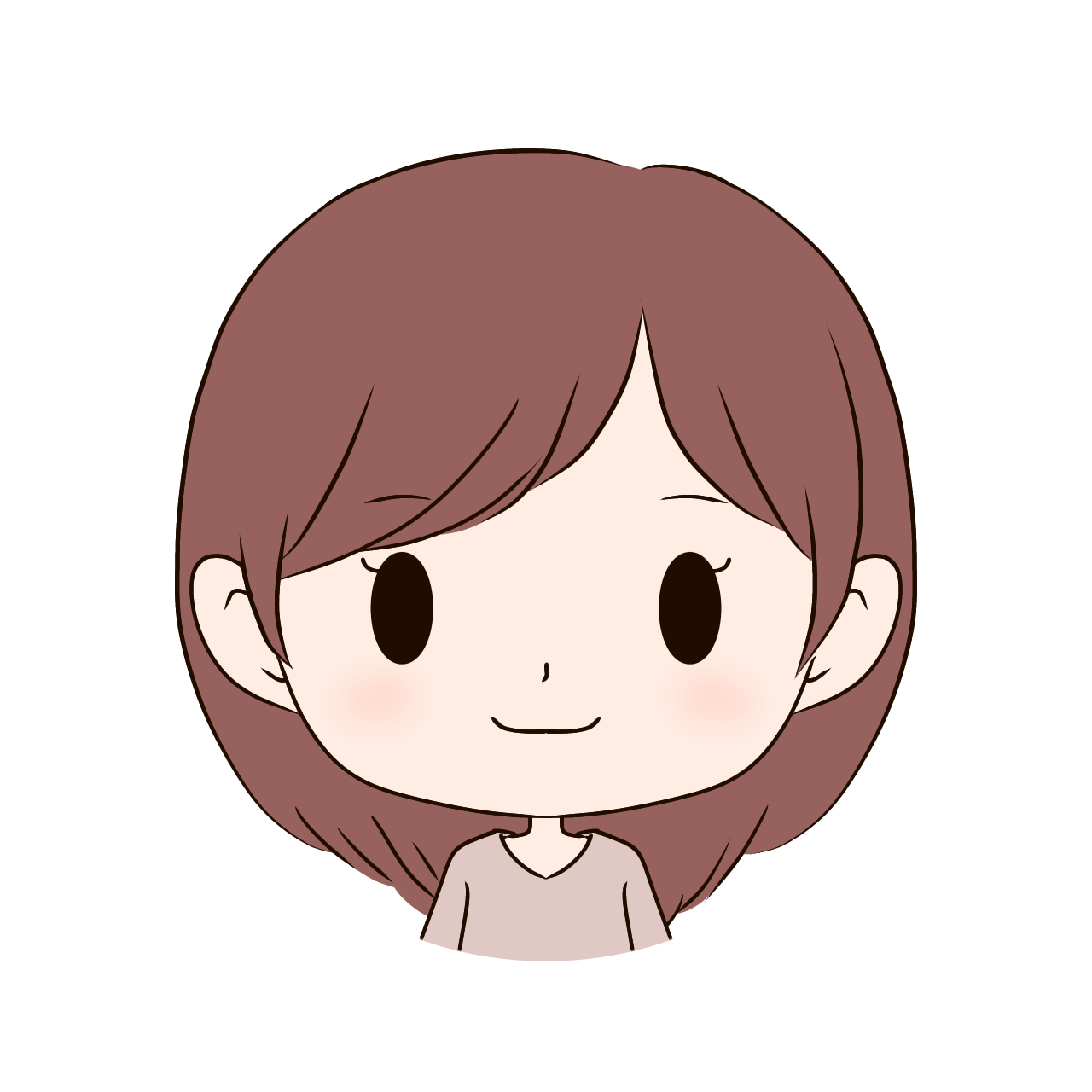
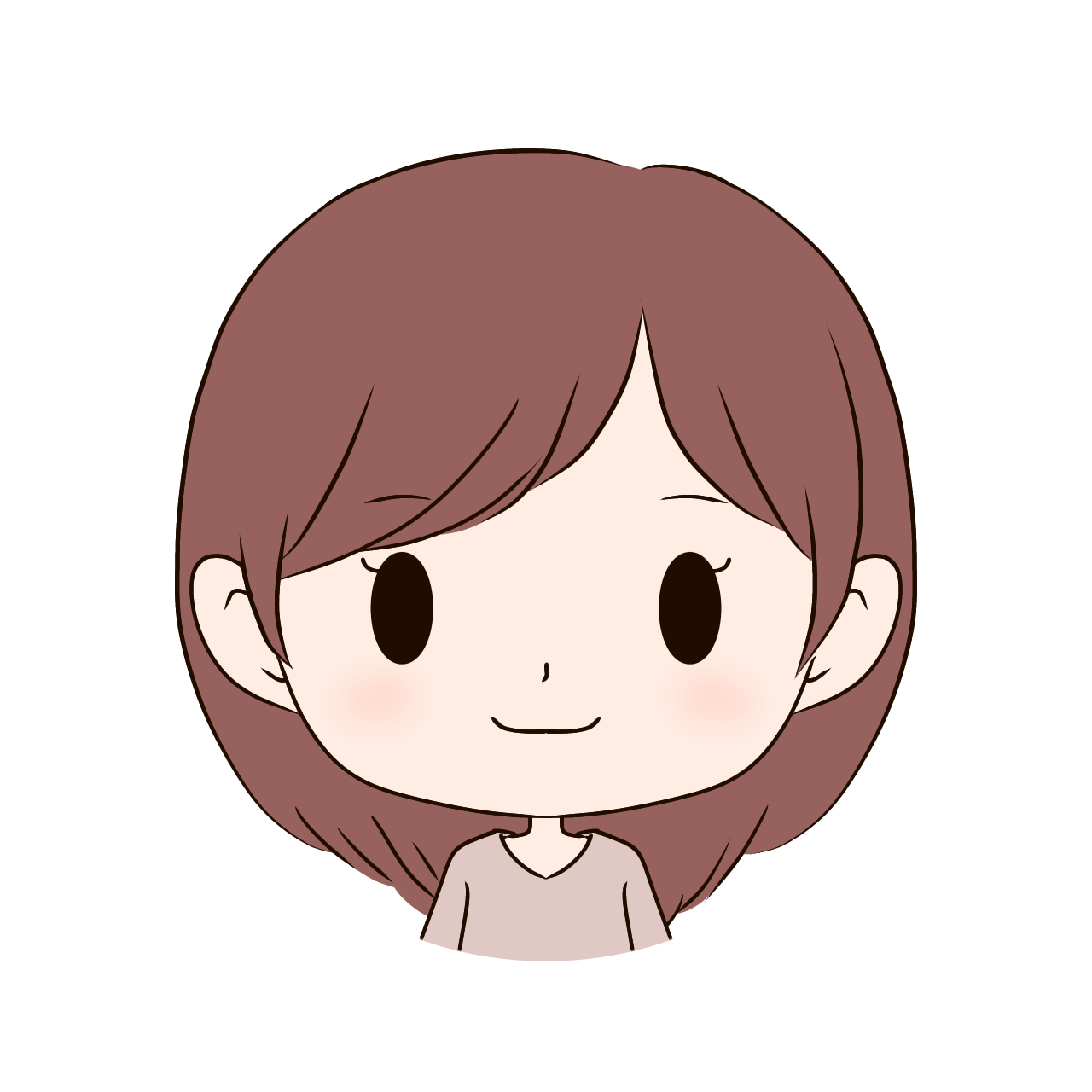
産地の特徴や人物名、年表などをノートにまとめるのもおすすめ!
ベーシックに比べて難易度が上がるとはいえ、合格率は約75%と民間資格の中でもかなり高めです。
「ある程度ちゃんと勉強がしたい」という方は、はじめからアドバンスを受験してみるのがおすすめです。
- 紅茶の知識を深めたい
- 勉強時間を確保できる
私はいきなりアドバンスを受けましたが、根を詰めることなく楽しく勉強できました。
ベーシックとアドバンスを比較してみよう
級位ごとの出題範囲や難易度をご紹介しました。
受験したい級は決まりましたか?
最後におさらいとして、まとめてみました。
- 紅茶について初めて学ぶ
- 手軽に検定を受けたい
初級がおすすめ
- 紅茶について幅広い知識を得たい
- 勉強時間を確保してゆっくり勉強できる
中級がおすすめ
紅茶検定は紅茶のいれ方や歴史、ブランドの背景など紅茶にまつわる幅広い知識を身につけられます。
学べばきっと普段のティータイムがさらに楽しくなるでしょう。


私は実際に紅茶検定の勉強をしてみて、紅茶がさらに好きになりました。
今まで飲んだことのなかった銘柄を飲んでみたり、シーズンごとに茶葉を買って飲み比べしてみたり、今までにはなかった楽しみ方ができるようになりました。
紅茶好きのみなさん、紅茶検定でティータイムをさらに豊かなものにしてみませんか?
\ 全Pフルカラー!雑誌感覚で勉強できる! /
おわりに
紅茶検定の特徴と難易度、受験級の決め方のご紹介でした。
【ベーシック】
初心者や勉強時間があまりとれない人におすすめ
【アドバンス】
より詳しく、幅広い知識を身につけたい人におすすめ
気軽に受けたい方にはベーシックがおすすめですが、私のように趣味で検定をとりつつ紅茶の知識を深めたいという方はアドバンスから受験してみるのもおすすめです。
アドバンスと聞くと難易度が高そうに聞こえますが、紅茶検定はテキスト1冊を勉強するだけで十分に合格が目指せるので、初心者にも優しい検定といえますよ。
紅茶検定は紅茶好きのための検定ともいえます。
紅茶が好きな方であれば、楽しく勉強をつづけられるはずです。
誰でも気軽に受けられるので、みなさんもぜひ紅茶検定で紅茶の奥深さを学んでみませんか?